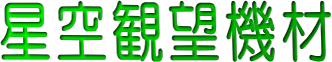
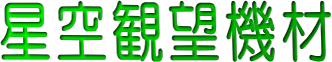
| オートガイドシステム構築 | ||
| ソフトウエアのインストールと使い方 |
|
|
| ソフト名称 | ソフト配布元 |
| Webカメラのソフト | UVC対応ソフトのためインストールソフトは不要。自動インストールとなります。 |
| 基板用ドライバーソフト | http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm |
| 今回は、くわなのほしぞら基板添付のCD内ソフトをインストールします。 | |
| ASCOM standard ソフト | http://mswwt.vo.llnwd.net/o25/ascom/ASCOMPlatform5a.msi |
| ASCOM standard | 今回は、くわなのほしぞら基板添付のCDに入っています。 |
| PDH Guiding ソフト | http://www.stark-labs.com/downloads.html |
| Stark Labs | 今回は、くわなのほしぞら基板添付のCDに入っています。 |
| 注) | くわなのほしぞらさんからリレー基板を購入したのはOSは、XP時代でした。 |
| よって、添付ソフトCDは、XP用のものでした。 | |
| 新OSについては、ネット上で配布されております。配布先URLを参照ください。 | |
| 新OSの基板ドライバーについては、ここを参照してダウンロードしてください。 | |
| リレー基板を購入すると上記の基板ドライバー、ASCOM、PHD Guidingは、 | |
| 添付CDに入っています。 | |
| PDH Guiding の使い方 | http://www.geocities.jp/tomtomshibata/phd_guiding/PHD.html |
| くわなのほしぞら | http://kuwana.ddo.jp/astro/TIPS/TIPS5.html |
| 星空観望日誌 | http://blog.livedoor.jp/tomoshiba_558/archives/50813914.html |
| 注) | 使用のカメラごと、カメラの種類を設定する必要があります。 |
| また、望遠鏡の機種に従い接続設定をする必要があります。 | |
| くわなのほしぞらの使い方説明で私が違うのは、カメラの接続と | |
| 望遠鏡の接続です。私の場合は、Windows WDM−style Webcam カメラです。 | |
| 各セットアップ状態により、Advanced setupが必要です。これをしないとまったく | |
| ガイドをしません。条件出しに時間を要します。 |
| Webカメラ TEMMA2 Jrの場合の使い方と設定 |
| 1)カメラの接続 |
.jpg) |
| 左下のカメラの絵をクリック |
| Windows WDM−style Webcam Camera を選択 → OK |
.jpg) |
| カメラの選択 |
| USB ビデオデバイス を選択 |
.jpg) |
| カメラモードの選択 |
| 640×480を選択 → OK |
.jpg) |
| USB ビデオデバイス 640×480の表示 右下表示がCameraになる。 |
| PC画面の表示は、600×480です。 |
| 2)望遠鏡の設定 |
.jpg) |
| 左下の望遠鏡の絵をクリック |
| Temma by Takahashiを選択 → Propertiesをクリック |
.jpg) |
| Temma Driver Setup の設定 |
| デバイスマネージャーでシリアルポートを確認 → そのポートを選択 |
| 今回の場合 COM6でしたので、COM6を選択 |
| 電源は、24Vで使用のため Power 24Volts を選択 |
| 望遠鏡の位置を選択 OTA−East Scope−Westを今回は選択 → OK |
| 赤道儀に搭載の望遠鏡の状態です。上記は、観望対象のある空が東で鏡筒が西と言う事です。 |
.jpg) |
| 同じく OTA−East Scope−West を選択 |
| 望遠鏡が西の場合です。東の場合は、OTA−West Scope−East。 |
.jpg) |
| 子午線の東の星に同期するの確認です。 |
| 右下表示は、Camera No Scopeです。 |
.jpg) |
| Mount(赤道儀架台)がconnected(接続)の表示。 |
| 望遠鏡の位置設定が決まると右下表示 Camera Scope になります。 |
| 3)ガイド星の選択 |
.jpg) |
| 左下の左から3番目の回る矢印をクリックすると Capturingになります。 |
| そして、ガイドする星を導入します。 |
.jpg) |
| 星を選択(四角い枠の中にガイドする星を入れるます。) |
| 4)ストップをクリック |
| 一度、ストップを押してからPHDのキャリブレーションに入ります。 |
| 5)PHD をクリック |
.jpg) |
| ハンドコントローラのトグルSWをHS(ハイスピード)にします。 |
| その後、PHDをクリックします。 |
.jpg) |
| キャリブレーションが始まります。W(RA+)→E(RA−)→N(DEC+)→S(DEC-)の順に行われます。 |
| 所要時間は、25〜45秒程度です。 |
.jpg) |
| ガイドが始まります。即座に、STOPをします。 |
| 星は、オリオン座のリゲルで実施。口径は、Φ24mmに絞る。この状態で |
| 上写真の様な小さな丸になります。カイドが安定したものになりました。 |
.jpg) |
| ハンドコントローラのトグルSWをNSにします。 |
| その後、再度PHDを押します。 |
| HSのままだとガイド時に一気に動き数秒でガイドNGとなります。 |
.jpg) |
| ガイドが始まります。 |
| Guidingの表示がされます。安定した追尾をします。 |
.jpg) |
| 40分程度、ガイドしていました。Star Saturated にもなっていません。 |
.jpg) |
| これは、星が大きな丸で表示されていた時の状態です。 |
| 星がずれてくると Star Saturated の表示がされます。 |
| ふらふらして安定したガイドでは、ありません。 |
| 完全に設定範囲を超えるとアイコンのある列が赤く点滅しチンチンを言う音がします。 |
| それでも修正機能は働き、赤い点滅は消えGuidingに戻る場合もあります。 |
| 30分程度で完全に復帰不可能となりました。 |
| 6)参考 |
| キャリブレーションは、次からのような順で行われます。 |
.jpg) |
| RA+ が基板のLCDに表示。LCD下部のRA+のLEDが点滅します。 |
 (700x525).jpg) |
| 四角い枠の中心を通る黄色い十字線が表示されキャリブレーションが始まる。 |
| 左下表示が W キャリブレーションとなります。 |
| 注) この説明では、小さなホコリ、ゴミを星と見たてて動かしました。 |
.jpg) |
| RA- が基板のLCDに表示。LCD下部のRA-のLEDが点滅します。 |
 (700x525).jpg) |
| 左下表示が E キャリブレーションとなります。 |
.jpg) |
| DEC+ が基板のLCDに表示。LCD下部のDEC+のLEDが点滅します。 |
 (700x525).jpg) |
| 左下表示が N キャリブレーションとなります。 |
 (2).jpg) |
| DEC- が基板のLCDに表示。LCD下部のDEC-のLEDが点滅します。 |
 (700x525).jpg) |
| 左下表示が S キャリブレーションとなります。 |
 (700x525).jpg) |
| ガイド状態となります。 |
 (700x525).jpg) |
| 左下表示が Guiding となります。 |
| これでオートガイドが始まります。 |
| 7) 赤道儀ガイド修正速度の変更 |
.jpg) |
| TEMMA2 Jr ハンドコントローラの設定(重要) |
| ガイド修正速度の変更が必要な場合の操作方法です。 |
| 修正速度の変更は、必ず必要です。 |
| 私の場合、赤経方向の修正速度を増速1.5倍に設定しました。 |
| 取説抜粋。取説しわクチャにて済みません。 |
| 8) アドバンスド セットアップと望遠鏡の設定(重要) |
| この設定をしないと正常なガイドを行いません。最適条件を捜す必要があります。 |
| 望遠鏡の設定でmoreを押すと左の設定画面に入ります。 |
| 脳みその絵を押すと右の設定画面に入ります。 |
.jpg) |
| Dec guide mode は、Auto指定です。上画面の設定データが本システム での現状一番良いガイド状態(40分 guiding)の値です。 Force calibrationを選択しないとキャリブレーションをしません。 モーションコンロールは、逆転させてください。 信号出力は、配線は間違ってないので変わりません。 プログラムの中身の考え方の様です。逆転の方が安定して長時間ガイドします。 |
| 設定の内容説明は、くわなのほしぞらさんのHPに記載されております。 |
| ここの脳みその絵(アイコン)のところを参照ください。 |
| 9) 望遠鏡の設置 |
| 今回、この設定の条件出しは、自宅2Fのベランダで行いました。 |
| 赤道儀は昼間に太陽で追尾から赤道儀の位置を合わせておきました。 |
| 緯度は、いつものまま三脚の水平を取り、極軸望遠鏡のあわせはしていません。 |
| この状態で、40分間程度のガイドをしておりました。 |
| 自宅で北極星が見えなくても、40分間露出のガイド撮影が可能になりました。 |
| しかし、自宅では、せいぜい2分程度で露出オーバーですが・・・。 |
.jpg) |
| 鏡筒:A80SS(ビクセン) 架台:EM11 TEMMA2 Jr(高橋製作所) 脚:AL三脚(ビクセン) |
| 10) 他条件出しの記録 |
.jpg) |
| 上記写真の様、VMC110Lは、合焦します。 |
| よって、VMC110Lでガイド確認をしてみました。 |
.jpg) |
| 方位磁石で北を合わせ水平をだしただけです。Webカメラは、ケンコーのデジタルアイピースです。 |
| 期待しましたが結論は、置いただけでは、40秒程度でガイド不能でした。 |
| しかし、A80SSと鏡筒を交換してみましたが、やはり40秒程度でNG。 |
.jpg) |
| 使用しているWebカメラですが、直焦点で合集させても点とならず、面積を持った円となります。 |
| A80SSの場合は、PC上でΦ3mm程度。VMC110Lでは、Φ8mm程度の円となります。 |
| A80SSだと星として認識しますが、VMC110Lの場合は、star Lost で星として認識しません。 |
| ガイド範囲を上写真の様に広げる必要がでました。 |
.jpg) |
| Serach region(ガイド範囲)を50ピクセルにしたら星として認識しました。 |
| 2015.3.11 CCDをケンコーのデジタル接眼レンズで実施時 |
.jpg) |
| 北極星にシッカリ極軸をあわせて確認したてみました。庭玄関前で実施です。 |
.jpg) |
| VMC110Lだと導入に時間がかかり条件出しに時間を取れないのでA80SSで実施しました。 |
| しかし、どうもうまく行きません。 |
.jpg) |
| この条件で実施しました。 |
.jpg) |
| この少し後で Star Saturated になりました。まだ、復旧するとは思いますが中止しました。 |
| どうもAGA−1の様、長時間の追尾ができません。 |
| 星をシリウスで実施していたのですが、明る過ぎかもと思い、リゲルに変更。 |
| しかし、星と認識しません。星が面積を持った丸にしか写らないカメラに問題がありました。 |